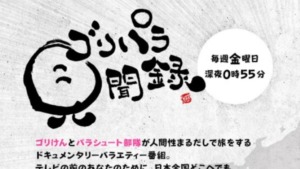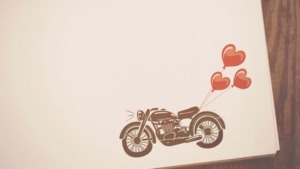ここ数年、電車やバスの優先席で色んなマークを見かけるようになりました。
有名なマークでは妊婦さんが使用する『マタニティマーク』というものや、外見ではわかりづらい障害や病気がある方の『ヘルプマーク』などがあります。
しかし、世の中にはたくさんの便利なマークがある一方で、認知度はあまり高くありません。
今日、試しにヘルプマークをバッグにつけて外出してたら子供連れのお母さんに「何あれ?頭のおかしい人が持つやつ?近寄っちゃダメよ」と言われました。もっと浸透して欲しいなと実感しながら家に帰って泣いてしまいました。
— イルカスミきよら #とまスク (@kiyora0635) November 7, 2018
きちんとした知識が広まっていないために、こんなことが起こってしまうのはすごく悲しいですね…。
私自身も数年前にパニック障害を患ったことがあり、普段の生活のなかで周囲の方の助けが必要な場面があることを実感しました。
その存在やマークの意味を知ってもらうことで、誰もがもっと安心して外に出られるような環境になることを願ってやみません。
”〇〇マーク”とよばれるものに少しでも興味をもってくださり、マークの意味をひとりでも多くの人に知ってもらえればと思いこの記事をまとめました。
ぜひ知ってほしい4つの”〇〇マーク”
ヘルプマーク

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、作成したマークです。
出典:東京都福祉保健局
まずご紹介するのは、冒頭でも登場した『ヘルプマーク』。
外見ではわからない障害や病気の方が、周囲に理解や配慮をお願いするためのマークです。少しずつではありますが、最近はテレビや新聞などで取り上げれる機会も増えてきました。
ヘルプマークの裏面には、どういった障害があるのか等を書き込むところもあります。
- 障害や病気のこと
- 周囲の人にお願いしたいこと
- 緊急連絡先 など
ヘルプマークってマークだけじゃ判りにくいよな…と思って画像検索したら、タグの裏に病状などを書くところがあるんだね それなら自分にも助けることができそうかもしれない #ヘルプマーク pic.twitter.com/6HHHGtZyMi
— 白波オルカ🦐@ガラルマサラ (@shiranami_oruka) November 8, 2018
外見だけでは私たちと変わらないように見えても、ハンディキャップを抱えている人は世の中にたくさんいます。もし電車やバスの中でヘルプマークを付けている方を見かけたら、席を譲るなどの配慮を。
もっと多くの人にヘルプマークの意味を知ってもらい、認知度が高まるといいですね。
マタニティマーク

妊婦さんが交通機関等を利用する際に身につけ、周囲に妊婦であることを示しやすくするものです。また、交通機関、職場、飲食店等が、呼びかけ文を添えてポスターなどとして掲示し、妊産婦さんにやさしい環境づくりを推進するものです。
出典:厚生労働省
続いてご紹介する『マタニティマーク』は、使ったことがある人や見かけたことがあるという人も多いと思います。
このマークは、その名の通り妊婦さんが使用するものです。見た目も可愛くて素敵ですよね!
仕事や通院など、妊娠中でも電車やバスを使わないといけない女性ってとても多いんです。お腹が大きくなれば妊婦ということにすぐ気づいてもらえますが、妊娠初期はもちろん、人によっては後期でもお腹が目立たない女性もいます。
そんな時に役立つのが、このマタニティマーク。
今日あった嬉しいこと
— グロール (@1san0) January 30, 2018
安産祈願の帰り1人で電車に乗って席いっぱいだったので立ってました。でもしばらくしたら男性の方が妊婦さんですか?座って下さいと声をかけてくれました。助かりますとお礼を言って座ることができました。もう嬉しくて涙出そうでした。鞄にマタニティマーク付けててよかった。 pic.twitter.com/Z5aDNdcaKM
電車やバスで席を譲る、気分が悪そうだったら声をかける、近くで喫煙しないなど周りができることは色々あります。
妊婦さんが安心して外に出られるように、マークをつけている人がいたら少しだけ気を配ってみましょう!
耳マーク
【耳マーク】は聞こえが不自由なことを表す、国内で使用されているマークです。
— ディーキャリア発達チャンネル@発達障害啓蒙アクション (@d_channeljp) November 4, 2018
全日本難聴者・中途失聴者団体連合会は、#聴覚障害 への理解を促すために耳マークグッズを作成し啓発をおこなっています!https://t.co/WfgHBhJLqj … pic.twitter.com/xfpGK0tRkE
聴覚障害者は、障害そのものが分かりにくいために誤解をされたり、不利益なことになったり、危険にさらされたりするなど、社会生活の上で不安は数知れなくあります。(中略)「耳が不自由です」という自己表示が必要ということで、考案されたものが耳マークです。
出典:社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
聴覚障害は見た目で判断することが難しく、それが周りに伝わらないことで不便な思いをしている方が多くいます。『耳マーク』は、そんな聴覚障害のある方が周りにコミュニケーションの配慮などを求めるために作られたマーク。
「もしマークを付けている人を見かけても、手話も使えないしどう接したらいいのか分からない!」という人もいると思いますが、手話が使えないからといって不安がる必要は全くありません。
- 口元を見せて話す(口話)
- 文字で伝える(筆談)
口元の動きから言葉を読み取る口話、文字で会話をする筆談など、コミュニケーションを取る手段は色々あります。
☆私は以前サービス業をしていて実際に聴覚障害がある方と接する機会がよくあったんですが、口話と筆談を活用することでスムーズに対応できていました。
気負わずに、自分ができる範囲でサポートすれば大丈夫です!
ハート・プラスマーク
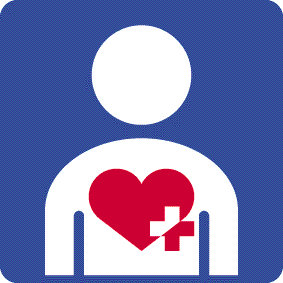
「内部障害・内臓疾患」というハンディがこの国ではまだ充分に認識されていません。内臓に障害があっても、外観からは判らないため “自宅で”“電車の中で”“学校で”“職場で” “スーパーで” 「辛い、しんどい」と声に出せず我慢している人がいます。一般社会にそんな人々の存在を視覚的に示し、理解の第一歩とするため、このマークは生まれました。
出典:特定非営利活動法人ハート・プラスの会
『ハート・プラスマーク』は、見た目ではわからない内部障害や内臓疾患がある方のマーク。本当はツラいのにハンディが周りに伝わらず、我慢をしている方のために作られました。
例えば、内部障害のある人がスーパーの駐車場で優先スペースに車を停めていたとします。内部障害は外見では分からないので、「あの人ちゃんと歩いてるのに何であそこに停めてるの?」と白い目で見られちゃうことがあるんですね。
そんな誤解を受けないためにも、とても大切なマークなんです。
認知度はまだまだ低く、初めて見た方も多いんじゃないかなと思います。ヘルプマークやマタニティマークに比べると、街中で見かけることも決して多くはありません。
外見ではわからない障害がある方も暮らしやすい環境を作っていくうえで、このマークがもっと広まることがとても大切です。
建物などに表示される”〇〇マーク”
次に建物やお店、電車などに使われているマークの紹介していきます。
障害者のための国際シンボルマーク

障害のある方が利用しやすい建築物や公共輸送機関であることを示す、世界共通のマークです。車いすを利用する方だけでなく、障害のあるすべての方のためのマークです。
出典:東京都福祉保健局
こちらのマーク、お手洗いや駐車場などで一度は見たことがあると思います。『車いすマーク』という名前ではなく、『国際シンボルマーク』という名前なんですね。
イラストの印象からか”車いすを使っている人向けのマーク”と思ってしまいがちですが、実は障害のある人全ての向けて作られたマークとのこと。様々な障害があっても利用しやすい施設などに表示されています。
盲人のための国際シンボルマーク

視覚障害者の安全やバリアフリーに考慮された建物・設備・機器などにつけられています。信号や音声案内装置、国際点字郵便物、書籍、印刷物などに使用されています。
出典:東京都福祉保健局
視覚障害がある人に向けて作られたマーク。音が変わる信号機の押しボタンなどに表示されています。
ほじょ犬マーク

身体障害者補助犬法に基づき認定された補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)を受け入れる店の入口などに貼るマークです。
出典:東京都福祉保健局
『補助犬(ほじょ犬)』とは、盲導犬・介助犬・聴導犬の総称。こちらのマークは、補助犬が入れるお店などに掲示されています。
駅やデパートなど大勢の方が出入りする施設では補助犬の受け入れが義務となっているので、補助犬を連れてお出かけされている方も最近よく見かけようになりました。
ちなみに盲導犬は『ハーネス』、介助犬や聴導犬は『ケープ』と呼ばれる表示をつけているので、普通のペットとは見分けがつくようになっています。

出典:厚生労働省
番外編 『白杖SOSシグナル』

「白杖SOSシグナル」普及啓発シンボルマークは、視覚障害者が外出の際、周囲の助力を求める必要がある場合に、白杖を頭上50cm程度に掲げることで助けを求める意思表示を行い、周りの人から手助けをしてもらうための手段。
最後にマークとは少し意味合いが異なりますが、ぜひ知っておいてほしいのが”白杖SOSシグナル”というもの。
白杖SOSシグナルとは、視覚障害のある方が周囲の助けを求める際に白杖を頭上に掲げるサインのことをいいます。
視覚障害者が助けを求めて白杖を掲げる「白杖SOSシグナル」がSNSを通じて拡散し続けている。シグナルを見ても「腕や白杖を急に引っ張らないで」注意点を挙げながら、理解がさらに広がることを期待している。
— 無外流の狼 (@miburou3) December 24, 2015
※これはもう一度広げないと… pic.twitter.com/E4eAerKmFy
2、3年前にSNSで拡散され、少しずつ認知が広まっているこのシグナル。その一方で、実は「拡散してほしくない」という声もあるんです。
白杖SOSシグナル運動について。 これは全国の視覚障害者が納得して提唱している運動ではありません。 また、危険な状況にもかかわらず、この合図をしていないということで 「困っていないんだ」と思われてしまう状況も起きています @Yano_Akiko @honma_dekka__
— kano (@kano47) May 12, 2014
周囲に助けを求める時にすごく便利なサインではあるもの、”合図を出していない=困っていない”という誤解を生んでしまう問題も抱えているんですね…。
大切なのは合図を出している・出していないに関わらず、困っている人や危険な状況に気づいて声をかけること。これは白杖SOSシグナルにかぎらず全てに共通して言えることだと思います。
白杖SOSシグナルをSNSで拡散している人たちは善意でやっています。しかし、裏にこういった問題を抱えていることも私たちは知っておかなければなりません。
おわりに 色んなマークを知って、少しの気遣いと優しさを

まだ他にも沢山のマークがありますが、私が選んだ”特に多くの人に知ってもらいたいマーク”を紹介させていただきました。
- 電車の席をゆずる
- 困っている様子だったら声をかける
- あたたかく見守る etc…
特別なことをしなくても、ほんの少しの優しさと気遣いを周りがもつことで、みんなが今より暮らしやすくなります。
マークは普段の生活で、また災害時などにとても役に立つもの。ひとりでも多くの方に知ってもらうことが大切です。
ただし最後にご紹介した白杖SOSシグナルが抱える問題と同じように、「マークやサインを出していなくても助けを求めている人がいるかもしれない」ということもぜひ心の片隅に入れておいてほしいと思います。
困っている人を見かけたり、危険を感じる場面に遭遇したりした時は、ぜひ勇気を出して声をかけてみましょう!
だれもが安心して外に出ることができる社会になるといいですね(^^)/
他にもこんな記事を書いています